こんにちは☀
西オーストラリア州で兼業農家をしております、ナイーブMEです👩🌾
我が家は建築業との兼業農家ですが、ファームでは主にヤギを飼っています。

このヤギはBoer(ボア)と呼ばれる南アフリカ原産の品種で肉用のものです。
ヤギ肉はスーパーでは見かけませんが、肉専門店ならば置いているところはあります。
基本的にインド人やイタリア、東南アジア、ムスリム系に人気の肉です。
現在は約130匹のヤギがいてこれらを売買しているわけですが、そのうち大人のオスが何匹いると思いますか??
家畜農業でのオスの比率
正解は1匹です🐐
130匹のうち約30匹は産まれて5ヶ月以下なので、妊娠可能なメスヤギ100匹に対してオスが1匹です。
少ないと思われるかもしれませんが、家畜農業としてはそんなもんです。
厳密にはヤギの場合はメス50匹にオス1匹が理想ですが、干ばつからの復活に時間がかかっている現在の我が家では100対1でいい感じです。(オスとメスは同じエリアで飼っています。)
ハーレム状態ですが、そのくらいオスの発情は激しいのです。
たまに個人宅でメス数匹とオス1匹をいっしょに飼っているのとかを見たりしますが、メスがかわいそうで仕方がありません。
実際に、メスがかわいそうだからとオスを格安で売りに出している広告も結構あります。
売られるのはオスの運命
そもそも、基本的に売りに出されるのはオスで、メスは繁殖のためにキープされるのが一般的です。
オスはオスでも、去勢されているものが多く市場に出ます。
去勢されないオスヤギは、いわゆる種馬ならぬ種ヤギです。
血統的に優れているオスヤギや成長具合が秀でているオスヤギは去勢されずにハーレムへ、それ以外のオスヤギはドナドナのように売られていく運命なのです。
去勢してもメスヤギよりは気性が荒いので、新しく飼うペットとしてもあまり歓迎されません。
産まれた時からペットとして育てている場合は別かとは思いますが、私には経験がないので分かりません。
市場に出回る値段も、去勢オスヤギが一番安く、一番高いのはオス(種ヤギ)です。
ヤギの去勢
手術ではなく、生後2,3ヶ月で睾丸にリングをはめるだけです。




リングをはめた瞬間はメー!と悲鳴を上げますが、その後はケロッとしています。
時間とともに睾丸が小さくなってなくなります。
去勢することによって発情しなくなるので無駄なエネルギーを消費せずに済み、食べる量も抑えられます。
犬や猫の場合は去勢するとホルモンバランスが崩れて太りやすくなると言いますが、私の見ている限りヤギは特にそんなことはありません。
ちなみに、発情したオスヤギはものすごく癖のある味がするので食べられたものではないと言われています。
つまり、種ヤギでない限り去勢をしないと需要も下がるということです。
我がファームの場合
現在数を増やそうとしているところなのでたまにヤギを買いに行きますが、買うのはメスだけです。
そのメスから産まれた子ヤギのオスは生後2,3ヶ月で去勢し、バイヤーの希望サイズになると売りに出します。

あんなに可愛い可愛いと言っているのに売るのだなんて・・・
と思われそうですが、私は農家です。
ヤギのことをペットとは思っていません。
どこかで誰かに美味しく食べてもらえるならば、それはいいことだと思っています。
とはいえ、意識的に子ヤギのオスはそこまで溺愛しないようにしています。まぁ、去勢リングをした時点で子ヤギの方からも寄ってこなくなるので自然と乖離していきますが。
そして、3ヶ月もすれば親と共に完全放牧なので、どんなに懐いていたメスの子ヤギでさえも私のことなど忘れていきます。
そしてまた新しい子ヤギが生まれてくる、という繰り返しがファーム生活です。
オスの肉を食べる
このような去勢オスヤギに対する考え方は、おそらく他の動物でも同じかと思うので、基本的にみなさんが普段口にしている牛・豚・鶏肉のほとんどはオスのものかと思います。
※飼育数の多いファームの場合は若いメスも食肉用に売り出されます。
年齢で味や食感が違うとはよく言いますが、オスとメスで味が違うとかあまり言いませんよね。
繰り返しになりますが、ヤギの場合だと去勢していないオスは癖が強すぎて食べられたもんじゃないとは言いますが、基本的に去勢されていないある程度の年齢を過ぎた動物が食肉として流通することはほとんどないかと思います。
ちなみに、イタリア人は年をとった去勢していないヤギを好みます。その癖のある味でソーセージを作るのがいいのだとか。
そんな感じで、恐らく年を取った家畜はソーセージやサラミなどの加工食品としての需要があるようです。

ニワトリや乳牛の場合、卵や牛乳はメスから採れるので、オスは繁殖したい時以外には不要です。
何も生産せず餌を食べるだけならば、早く売ってお金にしたいというのが農家ってもんです。
こうやって、ほとんどのオスはドナドナ行きなのです。
ニワトリのオスの例
日本だと田舎の方に行けば個人宅でニワトリを飼っている人がいますが、オーストラリアだと田舎でなくても飼っている人はいます。
私のようにど田舎のファーム住まいならば何をどれだけ飼うのかは自由ですが、街暮らしだとそうはいきません。
各自治体で飼ってもよい動物やその数の制限が決められていますが、おそらくどの街・町でもオンドリ(ニワトリのオス)は禁止されているはずです。

私の住むファームエリアの町部分(人口300人以下)でさえも、オンドリは禁止されています。
なぜって、コケコッコー!とうるさいからです。
あの鳴き声はオスしか発しません。メスは卵を産むときにたまにポッ、ポッ、ポッ、ポッ!と鳴きますが、けたたましく鳴くのはオンドリです。
そのため、オンドリは家にいてもらっては困る存在なので、『無料で差し上げます』というオンライン広告をよく見ます。
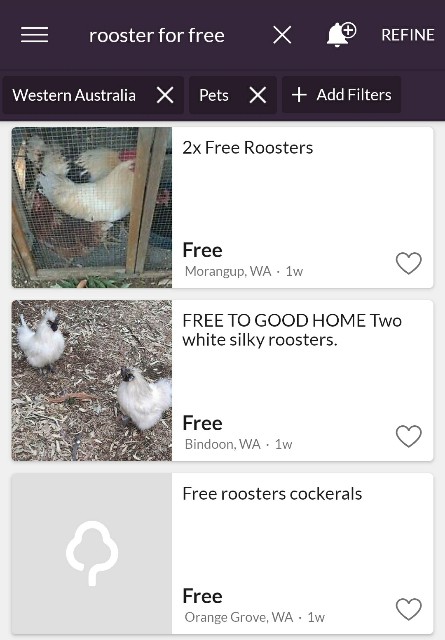
我が家でもオンドリは食べちゃいます。
朝4時くらいから鳴くわ、餌をものすごく食べるのに卵を産まないわ、オンドリが多いと争いが多いわで困っています。
現在10ヶ月のメス6羽に対してオスが3羽います。ここ最近争いが激しく、メスに対してオスが多すぎるので、近々2羽が唐揚げになる予定です。
旦那氏は普段肉を食べない人ですが、自分で絞めた動物はちゃんと食べます。
以上が家畜界でのオスの運命でした!
もしかしたら日本とは違う部分があるかもしれませんが、これは私の知る限りのオーストラリアの状況です。
最後にこぼれ話を。
田舎の方へ行くと飼っている動物を自分で捌いて食べる人は多いですが、基本的にはやはり名前は付けないそうです。名前があると愛着が湧いてしまいますからね。。。
しかし、ペットとして羊を飼っている近所のAさんはオスが産まれたら『ディナー』と名付けるそうです。
だって、産まれた瞬間から食べられる運命と決まっているからなんですって!