今週のお題「オンライン」
こんにちは☀️
西オーストラリア州で兼業農家をしております、ナイーブMEです👩🌾
新年度ですが、ほとんど?全て?の学校が閉鎖をGW明けまで延期すると聞いています。
オーストラリアでは先週より秋休みに入ったので現在学校は開いていませんが、国の考えとしては休み明けも学校は閉めない方向のようです。
その理由は、子どもには感染リスクが低いから。
しかしその裏には、親には働き続けていてもらいたいというのがあります。
オーストラリアは現在、飲食店や娯楽施設、公共施設などは閉鎖されていますが、スーパーマケットや薬局、テイクアウト専門の飲食店、医療機関、学校、保育園、公共機関(役所など市民のアクセスが必要な部門)などはエッセンシャルジョブとしてソーシャルディスタンスを考慮して稼働しています。
学校に関しては教員サイドは学校を閉めてほしいようですが、政府がどうも譲りません。
保育園に関してなんて、エッセンシャルジョブをしている家庭は保育料を無料にすることが決定しています💦現場は大混乱なようです。
ここまでの情報は、ど田舎で人に会わない(3週間街に行っていないので親族以外の人間を3週間見ていない)&テレビの無い生活をしている私の分かる範囲の情報なので、もしかしたら情報が古かったり現実とズレがあるかもしれませんのであしからず💦
※生の街を見たのは3/18が最後で、当時はまだ外出自粛も出ていない状況でした。今週後半には街へ買い物に行くので、生の街の状況は買い物後にまとめる予定です。
しかし、今日ここで言いたいのは
日本は学校閉鎖してるけどオンライン授業とかしてないよね?!そんなので、大丈夫???
ということなのです。
新4年生の姪の一日
先日、母と電話していたところ私の姉サイドの甥姪の様子を聞きました。
私の姉夫妻は病院勤務のため、子どもたちは保育園や学童に入っています。
このコロナで学校閉鎖がされてからも保育園や学童は開いているので、甥は保育園に通い続けこの3月保育園を卒園し、4月すぐから学童に入れています。
姪はこれまで学童でみてもらえていましたが、4月から4年生になったので学童には入れず自宅待機なのです。
しかし幸運なことに、義父(姪にとったら義祖父)が昨年度末で退職したので、姪の面倒をみることができるのです。
そんな姪と義父との一日の様子はこんな感じ。
- 8:30頃に義父が姪を迎えに行く(徒歩10分くらいの距離)
- 天気のいい日は、家の近くの河川敷を2人で数時間サイクリング(約7km)
- 帰ったら学校からの課題をやる
- ランチは調理実習という名のクッキングタイム
- 午後は、親の買ったタブレット教材で勉強したり絵を描いたり
なんかすごく充実していると思いません?!

それでふと思ったんです。
この子はこんなに恵まれているけど、子どもの面倒みれない家庭はどうなっているの?このままでは、学力の差が広がる一方では・・・
世界のオンライン授業と日本のパソコン教育
コロナによって世界各国でも学校閉鎖が相次いでいますが、ほとんどの国がオンライン授業に切り替えています。
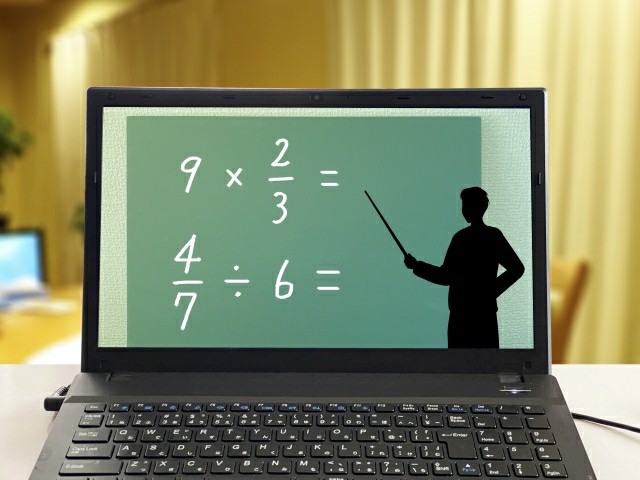
オーストラリアは国としては学校を閉める気はないみたいですが、自治体や学校単位で閉鎖をしているところも結構あり、その場合はやはりオンライン授業なようです。
うちには子どもがいませんのでオンライン授業の具体的な内容が分かりませんが、とにかく学校と子どもたちはオンラインで繋がっており、課題が定期的に出され、それを子どもも教師もすぐに確認できるシステムが整っているということです。家にパソコンがないならば、学校からタブレットの貸し出しがあります。
私の知る限りでは、一定の学年になったら授業にタブレットは必須で、日頃からタブレットを使った授業をしているようです。
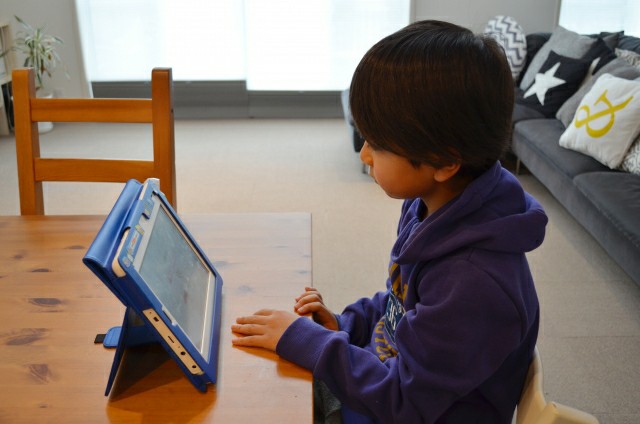
それに比べ日本の学校。
私は日本で小学校教師をしていたので、日本の公立学校のコンピューターを使った授業の状況は想像できます。
教師歴7年、勤務校3校、私が最後に勤務していたのは6年前ですが、まずどこの学校でも1人に1台パソコンが渡りませんでした。数が足らないのです。たいてい2人で1台をシェアさせます。

そして教師自体もパソコンに強い人が少なく、パソコン室に子どもを連れて行きたがらないのです。私自身もそうでしたが、自分でパソコンを使う分には大丈夫なのですが、40人の子どもが一斉に20台のパソコンを使うとなると、普段のパソコン使いとはわけが違いかなりストレスです。集団用の特別な操作も必要です。
パソコン室専門の教師がいてくれたら話は別ですが、学校現場にそんな余裕はなく、パソコンのメンテナンスもままならないまま放置されたパソコンは一台ずつ調子が悪くなり、35台あるパソコンのうち正常に起動するのが20台だけとかになるのです。
あくまで6年前以上の話ですが、たった6年前にパソコンに対してそんな状況だった学校が簡単にオンライン授業に切り替えられるとは思えません。
学校閉鎖が続くことで懸念される学力の差
恵まれた姪の話を聞いて、昔の教え子Aのことを思い出しました。
Aの両親は共働きで、朝も昼も夜も働いていました。両親は仕事にめいっぱいなのでAに構っている余裕がなく、生活環境が整っていないAは学校に来るだけでも大変でした。
もし、このコロナの状況下でAが家に一人でいたら・・・と想像したら絶望的な気分になりました。
もちろん、家庭環境がよろしくない家庭には家庭訪問を繰り返したり特別な配慮をしますが、それにも限界があります。
学校閉鎖後には、学校現場ではどうしようもない学力の差に直面するのだろうなぁと想像します。
学校閉鎖をするならば、必ず子どもをみる責任者が必要です。
それによって仕事を休まなければならない人は当然いるわけです。
その人たちを政府が保証すべき(給付金の配布など)なのです。
でも日本の現実は仕事は休みにならない、仕事が休めたとしても保証されない、そもそも外出自粛がままならないような状況だと聞いています。
何だかものすごく悲しいです。
姪の学校はGWまでは地域別に週2回8~10時だけ登校し、各クラス少人数で課題や家庭状況を確認するそうです。
オンライン授業ができないならばそれしかないと思います。
きっと学校現場も、閉鎖期間中はこれからの最良の策を考え続けていくことだと思います。
各家庭、できる限り子どもたちの知的活動(勉強だけではなく各活動)に協力できるような世の中であってほしいです。